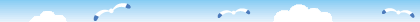
四万十川ウルトラ
マラソンへの挑戦
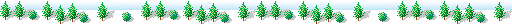
○章をクリックすると そのページにとびます。
三十代も後半を迎え、日々の生活にも慣れがでてきた頃、
高校時代の級友が田舎に帰ってきたことから、今まで止まっていた
おんちゃんたちの何かが少しずつ動き出すことになる。
浅利公教、高校時代一緒に遊んだ仲で、よく友達の下宿に遊びに
行ったり、休憩時間に学校を抜け出して近所の老夫婦の店に行っては、
いなか寿司を食べたものだ。
その老夫婦は、私たちが行くと必ずお茶を出してくれ、親切にしてくれた。
懐かしいころである。
浅利は、家の都合で東京のNTTをやめての帰郷だった。
その頃は彼も独身で、いろいろと遊び回って田舎の生活を
楽しんでいたようだ。
私の方は、ちょうど勤務先が変わった時で、
好きで六年間続けた少年サッカーの指導も終わり、そろそろ
厄年を迎えようとする頃であった。
何か物足りなさを感じていた時だった。
突然、浅利から厄入りとなる我々同級生の健康を祈願して、
足摺駅伝大会に参加しようという話が持ち上がった。
さて、3年4組で走るとなると誰がいるかな、ということで、候補に
上がったのが、陸上経験者の村越、彼が一区を走ってくれれば
後は何とかなるだろうということで、警察で日頃からトレーニングを
積んでいる石神、それから、走ることには全然縁のなかった松木、
サッカーをしていたので、走れるだろうと私、それから、浅利と
剣道の江口、後、何人かに声をかけ出場することになった。
おんちゃんたちの秘めた何かがこうして動き出したのである。
あれから、5~6年経ったか。足摺駅伝は毎年の恒例行事
として続いている。後の一杯のうまいこと。成績は関係ないのだ。
すると昨年、何を思ったのか、松木が四万十ウルトラマラソン
60kmの部に駅伝のメンバーを応募したということ、走るのは
苦手な部類に入るはずの松木の行動に、びっくりしたことだったが
不思議におんちゃんたちは誰一人反対もしなかった。
こうなると抽選の結果がどうなるかであるが、その結果、
村越にとっては、不運だろうが、私にとっては幸いにも大会の
抽選にはずれ、松木と石神、浅利の三人が出場することになった。
大会の日は、村越は役員として参加、私は妻と娘と三人で
応援に回り、岩間の沈下橋まで応援したことだった。
なんと、おんちゃんたち三人は、見事ゴールインしてしまい、松木の
感動話は一年中続くこととなり、そしてまたも松木の強引さに
おんちゃんたちは誰一人反対せず、今年も駅伝メンバーが
ウルトラマラソン60kmの部に応募することになったのである。
最悪のことに、今年は村越も私もそして、昨年の三人も大会に
出場できることになったのである。
石神については、抽選からもれていたのだが、顔の広い松木は、
あちこちの飲み友達に手配をして、しっかり100kmの部のあき
(走らない選手)を見つけてきたのだ。
ふつうならば、ちょっと敬遠したくなるところだが、さすが日頃から
鍛えている警察官は、強い、いずれは挑戦してみたかったと、
OKしたのだ。
こうして石神は100kmに残りは60kmに挑戦することとになり、
幕は切って落とされた。西暦2000年、なんと区切りのいいことか。
出場がはっきり分かった七月の初旬は、ぜんぜん実感もなく、
まだまだ先のことだとマイペースで、ふだんのように週1~2回の
練習をしていた。松木からは、時々調子伺いの電話がかかって
きたが、まるで人ごとのように思っていたのである。
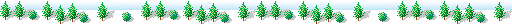
七月の終わり頃、練習の時間にも恵まれてきたこともあって、
一度「ふるさと林道」の往復を走ってみることにした。
スタートして1kmを過ぎてから急な坂があり、トンネルを下ると
横道の部落に入る、ここまではふだんも走ってきたこともあり、
しんどいながらも走ってこれた。横道からは、ゆるやかな坂道があるが、
これが案外きつかった。
トンネルを過ぎると長い下り坂が続く、下りは勢いで走れるが、
下りの走りにもテクニックが必要なことをこの頃は考えなかった。
益野の信号の折り返しというとこまできたが、今からまた6km帰ると
考えるとだらしかった。
帰りは、だらだら坂が長く続くのでこれがしんどい、なるべく
休まないようにとゆっくりと走ったがほんとにきつい。
横道を過ぎ、大岐の平野に来たときは、もうかなりバテバテだった。
家の前に着くなり、すわりこんでしまった。
しばらく、動くこともできずにいた。時間は、105分、12kmを走るのに、
それだけかかってしまった。
これでは、なんともならないと遅ればせながら練習計画を考え直した。
ふるさと林道往復の力がついていないのがわかった。
まずは、この往復が楽にできるようになることを目標として、
とりあえず横道を過ぎるトンネルあたりまで、走ることにした。
1kmあたりを8分~9分ぐらいのペースで走ってみる。
どうしても、坂道でペースがつかめない、あたりまえのことだが
無理をせずにしんどいときは早歩きもとりいれた。
通行量の多い休日には、たくさんの車と遇うわけだが、
中には知り合いもいるわけで、こちらは、帽子をかぶって走っているので、
まして、だらしい中で、車をみることもないのだが、
「走りよったね。」の声を聞くようになった。
こんなことがあった。天気は、少し雨がぱらついている休日、
家を出ていつものようにふるさと林道を走り出す、
思うように足が運ばない。
後ろから、のろのろと走る車が何かの気配を残しながら追い越していった。
こちらの方を気にしているように感じた。
「誰だろう」、見たことのない車だが、何か気になる。
とにかく、ノロノロと走っていくと、追い越していった車が先の待避所に止まった。
どうも変だ。しかし、何か用事があるようにも見えるし、近づいていく、変化はない。
ちょうど車を追い越そうとするとき、窓ガラスがおりた、中の人が見えた。老人だ。
その老人は、何かジェスチャーで車に乗らないかとでもいうように、まねいている。
「乗っていかんかね。」とかすかに声が聞こえた。
「今、走っている途中ですので、かまいません。」
そう答えると、老人は納得したかのように窓ガラスをあげ、
ゆっくりと走り去って行った。
きっと私の走っているだらしそうな姿を見て、雨も降っているし、
乗せてやろうと思ったんだろう。心配してくれたんだ。
全く知らない人のやさしさに何かうれしくなった。
思わず乗せてやろうと思ってくれた人は他にもいたようで、
妻からきいたことだった。
そんなにしんどそうに走っているのかとなさけなくなったのも事実である。
休日以外はたいてい、大岐の平野を30分間走40分間走と
元中高陸上部の村越のメニューを参考にして、週3回は走るようにした。
足をあまりあげない省エネの走り方にも慣れてきた。
そして、少しずつではあるが、力はついてきているように感じた。
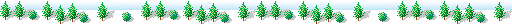
大会が近づいてきた。はたして走れるのか、足はもつのか、さまざま
な不安が出てくる。ふるさと林道の往復は、何とか走れるようになってきたが、
それでも不安だ。
そうかといって、長い距離を走ると足の疲労がたまってきて、足も痛いので、
休養が必要となる、そうかといって、何日もは休めない。
十月に入ってくると、そんな日々が続いた。
二~三日前の練習の疲労を残したまま、当日を迎えることとなった。
大会の一週間前、妻と四万十川に下見に出かけることにした。
妻には当日、遠くからの応援を頼んでいたのでどのあたりで、
応援するか、考えてみることでもあった。
中村から四万十川沿いに行く、道は工事で随分走りやすくはなっているが、
まだまだ道が狭いところも多くあった。
窪川回りで十川までやはり2時間はかかる。
十川から同じ道を帰る。ここからスタートするわけだ。
橋を渡って対岸を用井まで、途中で沈下橋を往復する。
ここの橋で写真を撮ってもらうことにする。ここまでは、大丈夫だ。
次に、半家の山越えになるが、予想がつかない。
そして、今回から加わる坂を下りてからの大橋の往復、ここでも、
写真を撮ろうと言うと、
「ここまで、これたらね。」と妻に言われ、なんということをと思い、
ことばに困った。プレッシャーは高まる。
用井まで。ここまでが第一段階、津ノ川の大橋を過ぎると岩間の沈下橋、
昨年三人を応援した場所だ。ここでも、応援してもらうことにした。
次は、中半の小学校を過ぎ、次に、中半の展望台あたり、
おそらく給水所があるだろう。口屋内を過ぎて中村市に入る。
窪川から鵜の江の間に、待避所の良いところ見つけた。
(ここで、長袖に着替えるよう。おそらく日も落ちているはずだ。)
夕方には、寒くなるとの情報は松木から何度も聞いていた。
四万十川を眺めながら家路に着く、じつに静かだ。
1週間後、ここを1500人ものランナーが走ることになる。
がんばらねば、だんだんと緊張が高まってきた。
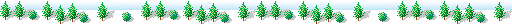
当日の朝、快適な朝とまではいかなかったが午前5時過ぎ頃目が覚めた。
6時頃少し早めの朝食をとり、足摺岬からくる浅利を待つ。
6時半ごろにくることになっていたが、6時20分頃に声がした。
彼も心は、はやっているのだろう。
妻の軽ばんミラで、中村へ向かう、バイパスの橋のもとで不破のほうに下りる。
市街地の方に行くとゲートボール場の真上の堤防のそばに松木の車があった。
すぐに、松木が出てきた。
半袖にジャージ、何かトレーニングに行くような軽装で少し驚く、彼らしい。
さあ、十和村へ出発だ。
天気は曇り空、時々雨がぱらついている。車の中では、リラックスして雑談が続く。
「ゴールしたらみんなで飲むぞ。」
もう、松木の心はゴールしている。昨年の成功は、相当の自信をもたらしている。
会社に無理を言って休みをもらっているらしく携帯で電話をしていた。
走るときも携帯を持って走るらしい。なんともおもしろい男だ。
いよいよ十和村に入る。沿道に車が大勢の人が見える。
何事かと見ると、すでに、100kmの部を走るランナーである。
(100kmのランナーは、とっくにスタートしているんだ。)
ここまで来るのにもそうとうの距離があるのにしゃっきで走っている。
彼らとは次元がちがうのだ、と自分を納得させるが、緊張は高まってくる。
行く途中にパラついた雨もあがり、こいのぼり公園は、
選手や関係者でにぎわっていた。
「受付がまだの人は、早く受付をすませて下さい。」
放送が流れている。
松木について受付をすませる。公園の端の方に陣取った。
ゼッケンとチップを靴につける。
「こんなもんで、ようタイムがわからあねや。」
文明の利器に苦手な松木のことばだ。
浅利を探してみると、受付で手間取っている。
ゼッケンの引換券を忘れたとのこと、きっと急いで家を出てきたんだろうな。
見渡せば、走っている選手、着替えている選手様々だ。
村越を見つけた。
ユニフォームには、「幡多陸競」の文字が見える。彼のプライドなのだろう。
目立つタイツにメッシュのシャツ、格好は決まっている。全国版である。
自分も着替えないと、この天気だと昼間は半袖で大丈夫と考え、
車の所で着替える。
アディダスのサッカー用の白パンに、白のTシャツ背中には、
「風になろう中高3の4」石神のデザインである。
みんなの所にもどると、浅利は、おにぎりとバナナをもらってきていた。
「腹へった。食べんかよ。」
バナナをもらい、食べる。朝食から時間も経っているし、少し食べておいた方が
よかろうと思った。
松木は、一服中、村越が来て、自慢のユニフォームとタイツのお披露目である。
間もなく、中村から乾さんがきた。
「がんばりましょう。」
健闘を誓う。
この乾さんが私の走りに大きな影響を与えることになるとは、この時は
予想もしなかった。
ステージでは、村の中学生による歓迎のセレモニーが始められた。歌が続く。
しばらくすると、開会式となる。特に気持ちの高ぶりもなく、リラックスして
妻と雑談をする。
その間にも対岸の道を100kmのランナーが走って行くのが見える。
15分前になったので、スタート地点に集まりだした。
応援に芝京子がかけつけてきた。彼女とは高校以来で懐かしかった。
いよいよスタート前、後ろの方で右側の端に並ぶ。
自分の時計は十時を過ぎたが、合図はない少し進んでいるようだ。
20秒ぐらいして鉄砲が鳴った。いよいよスタートだ。
この自分の時計が少し進んでいたのが、私のレースの運命をにぎる
ことになるのである。
集団が少しずつ動き出した。一番後方ぐらいの右側に並ぶ。
歩くような速さだ。先頭は、とっくに上の道を走っている。やっと登り坂にきた。
妻とことばをかわし、歩きながら坂道を登る。
長い長いレースが始まった。
坂に上に登ってみると、道の半分ほどに長い列が続いている。
後ろを振り返ってみると、ほとんど選手はいない。
ほぼ最後尾からの走りとなった。つまり、びりからのスタートになってしまった。
町中を過ぎる。十川の人たちが大勢応援してくれる。
橋を渡って、100kmのコースと一緒になる。急に選手が増える。
後ろからどんどんくるのは。100kmの選手なのだ。どんどん抜かれていく。
マイペースで走る。特に問題はない。
こちらのペースが上がったのか、三原のスナックののマスターと一緒になる。
彼も松木の飲み友達で、松木の話に乗って、今回の参加となった。
こういう人たちが何人かいたようだ。おそるべし、松木の影響力。
「松木は、先の方に行きよるろうね。」
「このペースで行ければ上等やね」
少しゆとりで走っていける。
10m~15m先をオレンジの服を着た女の子が走っている。
腕の振りが個性的だがペースが同じくらいなので、目標にちょうどよかった。
時間が30分経過したので、練習の時と同じようにストレッチをする。
わずか1~2分なのにあっという間に離される。
ストレッチをした方が足にはよいだろうと思っていたので、しかたがない。
そうするうちに、大きなカーブの所で松木を見つけた。
しばらくするとやっと声が届く距離まで追いついた。
「松木っ」
「おう、酒井きたか。」
しばらく一緒に走る。
さっきから、30分経った。ストレッチをする。
「酒井 大丈夫か。」
「大丈夫、大丈夫。」
見る間に距離が開く、追いつくべく走る。乾さんが見えた。かなりきつそうだ。
足をひこずっている。大丈夫かな。
しばらくして、止まりだした。足が痛いらしい。
乾さんを抜いて走り出す。
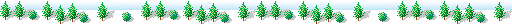
半家の山越え前の沈下橋の所まで来た。給水所だ。
水をとりながら、ストレッチをする。松木は、給水もそこそこに走り出す。
「止まったらいかん。次に動くときにいやになる。」
そういえば、彼が電話でよく話していたことだ。
沈下橋に下って行く。浅利と村越が沈下橋を折り返してきた。すれ違いに、
「半家の山越えを歩きようけん。」「???・・・。」
その後のことばは聞こえなかったが、追いついてこいや、
とでも言ったのだろう。余裕の二人に見えた。
沈下橋を走って行くと妻が待っていた。
今年は計測用の大きな時計がない。場所を変えたのだろう。
予定通り写真を撮って、折り返す。みんなを追いかける。
いよいよ山越えだ。
思っていたより、ずっときつい。
途中まで走ってみるが、これは無理をしない方がいいと判断して歩き出す。
周りもほとんど歩いている。歩きながら、ゼッケンの止めピンが
はずれていたので、上着をぬいでつけなおす。
かなり歩いた。やっと頂上にきた。
周りの選手はほとんどが走り出した。
どうしょうか迷ったが、しばらく歩くことにした。
目の前にも歩いているランナーがいる。
浅利と村越に遅れをとっていた松木は、この坂を歩くことなく走り続け、
二人を抜いたのだそうだ。昨年の経験はだてではない。
坂道を半分下りたときに走り出した。歩いているランナーを抜く。
下に大橋が見える。ここにも給水所があった。
ひざに水をかける。とても気持ちがよい。
そうしていると、橋の向こうから浅利がもどってきてすれ違った。
「よう、追いつかんで。」と声をかけた。
こちらは、しっかり休んでいるわけで、追いつくはずはないのだが・・・。
橋の折り返しに妻が待っていた。
「みんな行ったで。」
(なんとかがんばらねば・・・。)
走り出す、もうすぐ長生に着くはずだ。
しばらく走って、また、給水所だ。知り合いを見つけた。
川崎小の教頭、谷脇先生だ。昔の旧校舎だった頃、同じ職場だった。
ボランティアをしていた。もう一人男の人がいた。
よくその頃の稲田教頭に連れられて飲みに行ったお宅、誰だったか、
その時には思い出せず、「こんにちは」と言っただけだった。
後から、石川さんだと分かってとても残念だった。
ここで、少しゆっくりしすぎて、乾さんが走って行ったことを
気がつかなかった。
ちょっと時間をロスしたので、がんばって走るしばらく行くと、
乾さんが足をひきながら走っている。
いつの間に、と思いつつ、
「大丈夫ですか。」
「あれ、先にいっちょったに。」
「給水所で抜かれました。」
「もうすぐ用井です。用井までがんばりましょう。」
声をかけ合って走る。
用井まで行くと、残りが40kmとなり、100kmランナーにとっては、
大きなポイントであり、着替えの荷物も待っているのだ。
ここでゆっくりする人も多い。
60kmの部は、特にどういうこともないが最初の目標に
していたのは確かである。
乾さんは、足がよほど痛いのであろう。
少しずつ遅れだした。
心配をしつつもこちらもしんどいのは同じだ。
くねくねしたカーブが続き、なかなか前が見えない。
いきなり目の前が開けたかと思うと用井が見えた。にぎやかだ。
歩いて入る。公園に入ると妻が待っていた。
どうするのか。もう、やめるのか。不安な表情だったが、
スプレーを足にかけ、ポシェットをつけ、給水をする。
「足は痛いけど。やめるわけにはいくまい。」
歩いて用井を後にする。
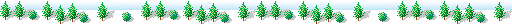
カヌー館を出てから、トコトコ走り出す。足の痛みは続いている。
藤の川の入り口に来た。
そこからは、しばらく歩いたように思う。
津の川の赤鉄橋が少しずつ見え隠れする。
また、走り出す。給水所に近づくと
「酒井さん、がんばってください。」
ボランティアの高校生が応援をしてくれた。
おそらくゼッケンから調べたのだろうが、名前を言われて、
びっくりしたことと、うれしかった。
ランナーにとっては、うれしい言葉かけである。
こういった心遣いがいろいろなところで見られた。
四万十川ウルトラマラソンは、このようにたくさんのボランティアの
人たちによって支えられているのである。
ひざに水をかけ、給水をして、歩き出す。しばらくしてまた走り出す。
このくり返しが続く。
「給水所では、必ず給水をしてください。」
「半家の坂道は、思い切って歩いてもいいです。」
「長距離を走ると足は大きくなります。
少し、大きめのサイズの靴がいいです。」
こう言ってくれたのは、靴を買いに行ったときに、
ていねいに話をしてくれた「井上スポーツ」の若旦那のことばである。
靴に走りが左右されることはわかっていたし、
少しでも負担がかからないように厚めの靴下も
栄養補給の薬アミノ酸も購入したのである。
もちろん、靴も0.5cm大きいのにした。この決断は正しかった。
それでも足の爪は、後に死んでしまったのである。
岩間の沈下橋手前に給水所があった。
膝が痛い。膝に水をかけるが状態は変わらない。
ゆっくりと歩き始める。たしかこのあたりにいるはずだが。
妻を捜す。沈下橋に下りるとき、遠くの畑の上に見つけた。
(えらい遠いとこにおるもんよ。)
手を振ると、振って答えた。
内心は、ひざが痛くて、ギブアップしかけていたのだ。
沈下橋を歩いて渡る。上り坂になるところでスプレーをする。
膝やももにかけるが、もう、このあたりになると効果があまり
分からない状態で、気休めのような感じだ。
足の痛みは消えない。だんだんと走る気がなくなってきた。
ただ、ただ、歩き続ける。なさけない。
「もう、しかたがない。」
「もう、走れない。」
「やはり、無理だったのだ。」
ギブアップを肯定しようと、様々なことばがうかんでくる。
それでも、まだ踏ん切りがつかずに、迷い、迷い、歩き続ける。
歩く隣を1000番台のゼッケンをつけたランナーが過ぎる。
100kmを走っている連中だすごい、おそれいる。
くやしさはないが何か寂しい気持ちでいっぱいだ。
もう、ギブアップを確信し、次の給水所をめざす。
妻は、岩間の沈下橋からずうっと歩いている私の姿を
向こう岸から見ていたそうだ。
いつまで経っても走らないのを見て、ギブアップするのを
考えていたそうだ。
次の、中半の小学校の給水所で待とうとしていたようだ。
ところが、運命は不思議だ。
私が、歩いている最中に、目の前にありがたくない
光景が現れることになる。
カーブを曲がったときだった。テレビの取材だろう、
地元のおばあさんたちが旗を振りながら四~五人で
応援をしている。そこの前を通り過ぎていくランナーを
撮影しているのだ。
中には、その前を平気で歩いているランナーもいるが、
自分としては体裁を気にしてしまう。
(なんでこんなところで。)
だんだんと近づいてくる。しかたがない走ろう。
足がなんと重い。
おばあさんたちの「がんばってよ。」という声を聞きながら
通り過ぎる。道の下からは、撮影の気配を感じる。
多少のがんばりを見せ、カーブを曲がったところで、
(もう、えいろう。)再び歩き出した。
この光景を対岸から見ていた妻は、私が走り出したのを見て、
なんとか大丈夫だと思ったらしく、中半の休憩所まで
一気に行ったようだ。
中半の学校で待つことで私のやる気が削がれることを
考えてのことだったようだが、ほんとはほんの100~200m
しか走っていなかったのだった。
もし、そこまで見ていたら、レースの展開はまたまた
大きく変わったことだろう。
そんな妻の行動を知る由もなく、歩いていた。
心の中では、自分の決断を肯定しようと
(もう、だめだ。)
(もう、無理だ。)
(しかたがないんだ。)
そんなことばかりを考えていたのである。
それでも、心のすみでは、
(ここで止めたら負け犬だ。)
(負け犬では終わりたくない。)という気持ちもぬぐい去ることが
できないままでいた。
その時だった、 「中高3の4がんばって。」
後ろから、声が聞こえた。隣にならぶ、若い男性だ。
「100kmの部にも、中高3の4のランナーが、いましたが、
だいぶ遅れていました。
もしかしたら、リタイヤするかもしれません。」
とっさに、石神のことがうかぶ。
60kmの部に申し込みながら、抽選でもれて100kmの部に
出場することになったわけで、昨年も60kmの部を悠々
ゴールした実績と今回も50km、60kmと練習を積んでの
本番であったのだが・・・。
「こんなからの大きい。」
「そうです。」
「ぼくは、中高の教師です。」と彼は言った。
なるほど、だから、声をかけてきたのか。
「まだ前に2~3人、中高3の4のランナーがおるけん。」
若い青年教師は、走り去って行った。
石神も遅れているのか。
ひょっとしたら、リタイヤするかもしれんな。
リタイヤを肯定する材料はふえた。
(よし、あの橋を渡れば終わりだ。リタイヤするぞ。)
もう、目の前に、中半小学校の大きな橋が見えた来た。
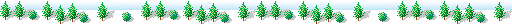
橋を渡り始める。
横に上下赤の短パン、ランニングのおじいさんが並んだ。
「どこから、参加ですか。」
「東京からです。」
「年は、いくですか。」
「70歳です。」
なんと、100kmを70才の老人が走っているのだ。
「何回も来るんですか。」
「今年で4回目です。もう、やめろうと思っているのだが、
一度も完走していないので、やめれんのです。
いつも、用井まで来ると、自分に甘えてしまって、バスに乗ってしまう。
今回は、最後まで走りたい。」
なんたる執念だ。
だが、リタイヤを決めていた私は、まるで他人事のように、
「がんばって下さい。」と声をかけた。
少しずつ、老人は、離れて行った。
この老人とは、この後、何回か会うことになったが、
きっと、完走したことだろう。
橋の上から、見る四万十川は、とてもきれいで、
川の底も透き通って見える。
橋を渡り終えた。目の前に、バスが止まっている。
(あのバスに乗るんだ。給水所で、休んでから
バスに乗ることにしよう。)
橋を曲がったとき、聞き覚えのある声がした。
「給水所で、ちょっと休んでいくぞ。」
「わかった。」
ふり向くと、なんと乾さんが走り込んできた。
誰かつきそいのランナーに励まされながら足をかばいかばい、
倒れ込むように来たのだ。
コンクリート上に、へたり込んで、肩で息をしている感じだ。
この時の気持ちは、どう表現したらいいのだろうか。
驚きと感動とすさまじいショックだった。
今までのギブアップ宣言は、消えていた。
足を投げ出して、しんどそうにしている乾さんを見て、
今まで歩いていた自分が恥ずかしくなった。
(足を引きながらも、懸命にここまで走ってきたんだ。)
(乾さんに比べれば、自分はなんだったんだ。)
(これでは終われない。終わるわけにはいかない。)
(まだ、がんばれる。)
(よし、ついて行こう。)
いつの間にか、走る勇気を取り戻し、走る態勢になる。
つきそいのランナーから声がかかる。
「もういかんと間に合わんぞ。」
「行こうか。」
乾さんたちが走り出した。こちらもついて走り出す。
1kmぐらい行った所で声をかける。
「乾さん。もうやめろう思いよったけんど、乾さんを見て、
また走ろうと思いました。ついて行きますよ。」
三人で走り出す。
乾さんは、よほど足が痛いらしく、走っていても、
急に歩き出したり、また、走り出したりかなりきつそうだ。
つきそいのランナーも中高の先輩で、100kmの部を走っていた。
乾さんを励まし、励ましのランニングだ。
だんだんと二人は、遅れだして、一人でのレースとなる。
中半の展望台に来たとき、待ちくたびれた表情の妻がいた。
(よっぽど待ったことだろうな。)
ペットボトルを受け取り、はたの給水所で、エネルゲンを
ボトルに補給し、ボトルを持って走り出す。
かっこうなんて、どうでもよかった。
後方に乾さんが見えた。がんばってるな。
こっちもがんばらねば。勇気が出てくる。
ボトルがポチャポチャ音をたてる。まだまだ、口屋内までは長い。
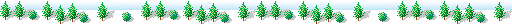
だましだましの走りでなんとか口屋内まできた。
通りの人たちの応援も高まってきた。
中ほどに沈下橋に下る道がある。そこに、wcの表示が見える。
ランナーのためのものだ。
自分は、走っている時は、一度もトイレにいくことはなかったのだが、
ランナーにはありがたい。
にぎやかな応援の声が聞こえてきた。
お年寄りの人たちが何人か手をたたいて応援してくれている。
「おう、こんなに手をたたいたら、明日は手がざまに、
はれちょうろうのう。」
思わず、笑ってしまった。
たしかに、そうだろう、もう何時間も通り過ぎていくランナーを
応援してくれていたのだろう。
ほんとに、ありがたいことだ。
「がんばってや。」
「がんばってよ。」
「ありがとうございます。」
声援はうれしい、がんばる力になる。
口屋内の赤鉄橋の下を通過。カーブを曲がり、
小さな橋を過ぎると中村市の標識が見える。
松木がよく言っていた。
「中村市に入ると、元気になるがねや。おらら、
やっぱり中村の人間やねや。」
ところが、こちらは、そうでもなく、
(まだ、遠いなあ。やっとここまで来たか。)
としか思わなかった。
やはり、中村の人間ではないのだ。
坂道になると歩いたり、平地や下り坂になると走ったり、
そのくり返しが続く。
足へのダメージは、相当なもので、きつい。
上久保川の辺りで、今までとはちがう痛みが足の裏にきた。
なかなか治りそうもない。足をかばいながら走る。
鵜の江の手前で、妻が待っている。
そこで、半袖から長袖に着替えねばと考えていた。
そして、果たして、ゴールに着くのだろうかという不安も
徐々に高まってきた。
このころになると、後ろを見てもランナーがぼつぼつと
見えるだけになった。
(だいぶ抜かれたもんな。)
(それにしても、ほんとに人が少ないな。)
右岸に、勝間が見える。保育園から小学校2年生まで5年間、
昭和30年代を生活した場所だ。
ここでの思い出はつきないが、そんなことを考えている
余裕はなかった。
足の痛みはとれない。歩きながら妻がいる場所を探す。
見えてきた。
「足の裏が痛い。今までとちがう場所よ。」
「大丈夫?」
「長袖に着替える。」
靴を脱いで、靴下の上からスプレーをかける。
半袖から、長袖に着替えて、走れるかどうかわからないまま、
とりあえず歩き出す。
後方には、人影もまばら、乾さんの姿もない。
鵜の江の直線に入る。
少しずつ走り出す。やはり、足は痛い。
この辺りになると、同じランナーを目にするようになる。
こちらが抜いたり、歩いていると抜かれたりで、同じ状況が続く。
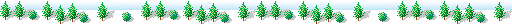
トンネルが見えてきた。坂道は歩き、トンネルに入ってから
走り出す。一人ランナーを抜く。出口から、下り坂だ。
少しは楽に走れる。
川登りの関門が気になりだした。
たしか5時46分がその時間だった。
「川登りまで後○km、時間は○分あります」
ボランティアの声が響く。
辺りは薄暗くなってきた。目の前に、上下赤の服装、
中半の橋で出会った老人だ。
ほんとに疲れている様子で、歩き走りの感じだ。
「関門まで、もう少しです。間に合います。
がんばって下さい。」
返事はないが、分かりましたという表情を見せてくれた。
この辺りになると、声援の声が違ってくる。
「おかえりなさい。」
「おかえり、おつかれさん。」
100kmの連中は、朝の5時半に中村をスタートして、
十和村、西土佐村、を経て、中村に帰ってくるわけで、
ほんとにお帰りなさいになるわけだ。
「おかえりなさい」は、重みのあることばである。
川登りに入る。ここにも思い出がある。
岡本虎猪先生、下ノ加江小学校に勝間小学校から転校して
行ったときの担任で、奥さんのしなお先生には、
勝間で担任してもらった。夫婦に担任してもらったのである。
虎猪先生は、とても厳しくて、こぶのついた竹を片手に持って、
ゴツンゴツンと叩かれたものだ。
でも、何故か好きで、小学校5年か6年の頃に、
何人かの友達と遊びに行った。
バスに時間が合わなくて、中村から、川平回りをしばらく歩いて、
やっとこさバスに乗った。
おでんをごちそうになって帰ったことだった。
まだ、元気でおられるだろうか。
その虎猪先生の家の近くに来た。
にぎやかな声援が聞こえてきた。若いお母さんたちが大勢で、
何かリズミカルなかけ声をかけながらの応援だ。
もうすぐ関門であることがわかる。
関門前で、乾さんと一緒に走っていた先輩がきた。
乾さんの姿は見えない。
「乾さんは、どうしましたか。」
「だいぶ、遅れちょうけん、関門で待ちようぞ。」
と言ってあるとのこと。
5時半頃に、川登りの関門を通過した。
余裕は、15分ほどしかない。妻が待っていた。
歩きながら、話す。
「どうなるか、思いよった。」
「あんまり、時間がないで。」
「歩からったら、佐田の関門に間に合うと。」
妻は、ゴールまでいく予定だったようだが、
あったかい紅茶を飲みたかったので、佐田で待つように頼む。
「ここまで、来たがやけん、がんばってね。」
その通りである。ここまで来たのだから。
暗くなった道をボランティアの車が電灯が照らしてくれる。
途中の給水所でペンライトを首にかけてもらう。
これがないとランナーが分からないのだ。
「ここまできたがぞ。」
「ここまできたがやないか。」
自分に叫びながら走り続ける。
時間は、どうだろう。時計のバックライトが役に立つ。
暗闇でも時間が分かる。しかし、ゆとりはない。
急がねば。佐田の関門は、6時46分だ。
暗闇の中、まるでゾンビのように、ゴールを目指すランナーたち、
私もその一人である。
佐田の関門は、遠く感じられる。時間だけは正確に過ぎていく。
(まだ間に合う。がんばらねば。)
大きな声が聞こえてきた。
「関門時間まで後5分。」「関門時間まで後5分。」
なんとか間に合った。妻の姿が見えない。
係りの人と話をしている姿が見えたがこちらには気がつかない。
声をかけると気がついた。
歩きながら、紅茶を飲む。とてもおいしい。
「関門時間まで後3分。」という声が聞こえた。
「ぎりぎりやね。」
「後ひとがんばりしたら、なんとか間に合うね」
と係りの人。
「走り続けたら間に合うろ。」
走り出す。妻はゴール向かった。
後6kmの所まで来た。中村の灯りが遠くに見え始める。
今どこなのかはっきり分からないが、走っていると、
わりとペースの速いランナーを見つけた。
並んで走る。何人かぬきながら時間が気になる。
ゴールまで後2kmぐらいのところにきた。
7時15分だ。後15分か。ふつうなら、なんでもないことだが、
この足の状態では、満足に走れないだろう。
「何時ですか。」
一緒に走っているランナーが問いかける。
「7時15分。」と答えると、
「大丈夫です。まだ間に合います。」という。
(この人は何を言っているのか。冗談じゃない。今の状態では、
1kmを7分ぐらいで走るのは、そうとうきつい。それに、
最後に丸の内の坂道がある。この人は知らないんだな。)
ペースを上げた。一緒に走っていたランナーを残して、
スピードを上げる。暗闇の中ボランティアの人たちが
照らしてくれる灯りでかろうじて道が確認出来る。
一人、ゴールを目指す。
不思議に足の痛みが消えた。いや、感じない。
(間に合うか、7時半までにはゴールせねば。)
ただひたすら走る。
百笑に入って、すぐに丸の内に上がる坂道だ。
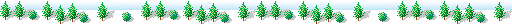
後2分。(きつい、きつい。)
坂道になった。なんとか走り続ける。
「急がんと間に合わん。」
声をかけてきたのは、後から追い抜いてきたランナーだ。
どんどん走って行った。
(がんばらんと。もうすぐだ。)
やっと坂道を越えた。火を焚いたり、応援の人もたくさんいた。
この中に、幡教社の社長である松岡さんがいたそうだが、
全然気づきもしなかった。
こんどは、下りだ。時計は、29分だ。
がんがん走る。右に回って下る。中高の裏に来た。
急に、応援の人が紙テープをかけてくれた。
ゆとりがあれば、うれしいのだろうが、それどころではない。
中高の入り口を左に折れるところで、妻の声が聞こえたが、
こちらは必死である。姿はよう見つけなかった。
(間に合うのか?)
(どうか?)
体育館の裏を走って行くと、ライトで急に明るくなった。
放送の声が聞こえる。
フェンスで仕切られた道を入っていく。
ゴール前、ランナーがいる。躊躇せずに抜く。
目の前にゴールテープが飛び込んできた。
係りの子からメダルをかけてもらう。
「やったぞ。」
「間に合ったのか。」
スタート地点、私の時計は20秒くらい進んでいた。
ラッキーだった。
目の前に、中高3ー4のメンバーの顔があった。
「がんばったねや。酒井。」
「ぎりぎりやったぞ。」
「よかったね。」妻が目の前にいた。
(間に合ったんだな。)
(よかった。)
やっとこさ立っている自分を、松木が椅子のある方へ
連れて行ってくれた。
石神、村越の握手、そして、浅利がポカリをわたしてくれた。
呆然として、ゴール地点を見ている。
時間はオーバーしている。まだ、ランナーが
ぽつりぽつりと帰ってくる。
参加賞のタオルが首にかけられる。
メダルをもらったのは自分が最後だったんだ。
どのくらい時間が経ったのか分からないが、
ぼうと回りを見渡して見る。
ぼつぼつと選手たちが帰りだしている。まだ、まだ、
ゴールを目指しているランナーは何人もいるのに。
放送が続く、拍手がおきる。
(やりとげたんだなあ。)
(終わったんだなあ。)
満足感、達成感、安堵感、いろいろな気持ちが入り乱れている。
それにしても、なんというフィニッシュなんだ。
われながらよくやったと思う。
自分の人生の中で、これほどぎりぎりのことはなかった。
何にしても、ある程度のゆとりを持って望むのが自分の
スタイルであり、今までの人生の節目においても
ゆとりはあったはずだ。
それなのに、今回はどうだ。
節目ほどは大したことではないかもしれないが、
自分にとっては大きな勝負であった。
それをこのようなぎりぎりで達成したのだ。
意外なできごとなのだ。こんな思いは、初めてだ。
痛い足を、石神がくれた氷で冷やしながらやっとこさ腰を上げる。
松木には悪かったが、祝福の一杯は、遠慮して浅利と帰ることにした。
石神と村越は元気だ。冗談も出ている。
清水への帰路につく。3人の話もはずむ。
「もう、絶対でんぞ。」
「これで最後やね。」
二度と走りたくない、そんな気持ちだった。
帰宅後、足は痛くて痛くてスローモーションのようになって
しまうが、子どもたちに話すのも何か誇らしげにできる。
もし、リタイヤしていたら、ふとそんな思いもよぎる。
痛い痛い体をかばいながら、床につく。
次の日、ひざに激痛がはしる。起きあがるのもつらい。
一日中、いや3日~4日も体は痛くてたまらないのに、
だんだんとマラソンのことがなつかしく思い出される。
(これなんだな。)と思う。
この痛みがだんだんと消えると、また、なつかしい思いが
いっそうふくらんでくるのだろう。
だから、毎年、チャレンジするのだろう。
ミレニアムの年、
四万十川ウルトラマラソン60kmの部
タイム、9時間29分59秒、
制限時間、一秒前、完走。
2000年、10月15日、
この日は、私の生涯の中で忘れることのない一日となった。
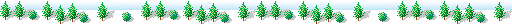
一度、二度、リタイヤを考えながら、最後までたどりつけた。
どうしてなのか。
確かに気持ちの面、根性や気力も大事だが、それよりも勝るもの、
それは、レースの間、共に苦しみながら走る仲間の姿なのではないか。
あの挫折しかけた中半小の大橋のたもとでのこと、
足の痛いのをこらえて走っている乾さんを見て心が熱くなった。
大きなパワーをもらったような気がした。
自分もまだがんばれるんだと奮起できた。
薄暗くなった佐田の近く、東京からきた70才の老人は、
体を傾けながら走っていた。いや正確に言うと歩いていた。
その背中を見たとき、
(ここで、がんばらねば。)と
追い抜いたときに、その老人から勇気をもらったように思った。
あれほど、足の裏やひざ、ももが痛くてたまらなかったのに、
ゴールまでのラスト2km、丸の内の坂道、
足の痛みは、感じなかった。
ただ、ただ、ゴールに着くことしか頭になかった。
あれは、集中力なのか、火事場のばか力なのか。
マラソンは不思議だ。筋書きのないドラマだ。
1500人のランナーがドラマを演じている。
長い長い時間、修行僧のように、一人一人が
戦っているんだ。自分との戦い、修行なんだ。
もしかしたら、人生のドラマと重なっているのかもしれない。
それは、四万十川を舞台に演じられた。
まさに、四万十川ウルトラマラソンだ。
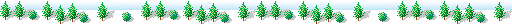
後日、11月中旬頃に送られてきたウルトラマラソンのサンプル
写真の中に、ゴールインした瞬間のがあった。
写真の中央に写っている後ろ姿は、まさしく松木であった。
「カメラの中央付近にどんとかまえて、じゃまになったろうに。」と
妻と話したことだが、
この後ろ姿から、松木の思いが伝わってきた。
「酒井は、もう間に合わん。」と思っていたらしいが、
それでも、こうしてゴール前で待っていてくれたんだ。
仲間がいることはうれしいものだ。
石神は、川登りの関門に間に合わなかったそうだ。
ゴールまでもうすぐの所まで来ていたのに残念だったろう。
中半で会った中高の先生は、ひょっとするとリタイヤするかも
しれないと言っていたので、それを思えば、がんばっていたのだ。
彼曰く、
「来年への足がかりが出来た。」と
すでに、来年に向けて心の準備は出来ているのだ。
来年も100kmに挑戦することだろう。
浅利は、
「もう、出んぞ。」という。
彼は、二度もこの大会を時間内に完走したし、
今年は、松木よりも先にゴールインしたのだから、
満足していることだろう。
昨年は、途中リタイヤしそうになったのを松木と一緒になり、
ゴールした。松木は、自慢げにその時の様子を一年間話し続けた。
これで、その話をすることもなくなるだろう。
彼の面目もたったわけで、めでたし、めでたしだ。
村越は、前回に続いてのリタイヤとなった。
あれほど調子よく浅利と走っていたのに、信じられない。
足に豆ができたのが原因らしいが他にも何かあったのかもしれない。
心の中では、悔しい思いがあるはずだ。
次のチャレンジはあるのだろうか。
松木は、絶好調で、すでに100kmの挑戦を宣言している。
彼のレースにかける思いはすごい。
あれほどのがんばりは高校時代の彼からは、
誰も想像できないはずだ。
さらに、周りを巻き込んでいくので、誘い込まれるおんちゃんたちは、
たまらない。それも楽しみなのかもしれない。
私は、もう3ヶ月も経とうとしているのに足のダメージが消えない。
そうとう、負担がかかったのだろう。
懐かしい思いは、消えないが、もう一度チャレンジとなると、
少し考えてしまう。
「風になろう」中高3ー4のメンバー、
2000年のチャレンジは終わった。
でも、おんちゃんたちの何かは確実に動き出してしまった。
この後、どんなことが起きてくるのかわからないが、
きっと何かを求めて新たなチャレンジが始まるのだろう。
四十半ばのおんちゃんたちは、高校の頃の
あの未来に向けた夢をこれからも追い続けることだろう。
2001年1月 執筆
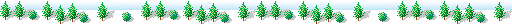

![]()