


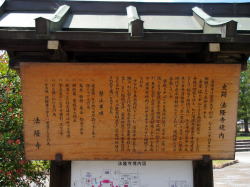




| 平成 27年 4月 17日(金) |
|
||||||||||
 |
  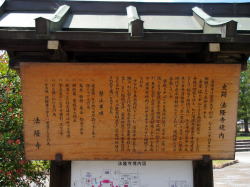 |
 |
   |
| ★南大門(国宝) 法隆寺の玄関にあたる総門。創建時のものは1435年に焼失し、現在の門は1438年に再建された。 |
  |
| ★中門(国宝) | ||||
| 西院伽藍の本来の入口となる中門。深く覆いかぶさった軒、その下の組物や勾欄、それを支えるエンタシスの柱、これらは飛鳥建築の粋を集めたもので、重厚な扉と、左右に立つ塑像(粘土)の金剛力士像は、日本に残っている最古のもの。 | ★金堂(国宝) 金堂には、法隆寺の本尊が、安置されている。周囲の壁面は、昭和24年に焼損したが、再現壁画として当時の美しさが蘇った。 |
|||
 |
 |
| ★五重塔(国宝) | ★大講堂(国宝) | |||||
| 「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」 | ||||||
| 五重塔は、釈尊(しゃくそん)の遺骨を奉安するためのものであり、仏教寺院において、最も重要な建物とされている。高さは約31.5mで、わが国最古の五重塔。 | 正岡子規の、生涯20万を超える句を詠んだの作品のうち、最も有名な句 法隆寺に立ち寄った後、茶店で一服して柿を食べると、途端に法隆寺の鐘が鳴り、その響きに秋を感じた、というのが句意 |
金堂と五重塔の間にある僧侶たちの研鑽の場。数ある法隆寺の建物の中でも最も大きく、ひときわ美しさが際立つ大講堂で、再建されたもの。かつては金堂と五重塔により近い位置にあったものが、925年(延長3年)に落雷で焼失。それから65年後の990年(正暦元年)に新築されたのが、現在の大講堂。 |
||||
 |
||||||
 |
 |
|||||
| ★聖霊院(国宝) | ★大宝蔵院 | |||
| 聖霊院(しょうりょういん)。聖徳太子を祀る堂。鎌倉時代に建立された建物で、現在の聖霊院は1284年(弘安7年)に改築されたもの。聖徳太子及び眷属像(平安時代、国宝)、如意輪観音半跏像(重文)、地蔵菩薩立像(重文)を安置している。 | 法隆寺の建物のなかで最も新しくできたものが、境内の一番北寄りにある大宝蔵院。 1998年(平成10年)に落成し、仏像をはじめ厨子や舞楽面などの工芸品を含む寺宝が多数展示されている。 |
|||
 |
 |
|||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★毘盧遮那(ビルシャナ)(国宝)【奈良の大仏】 聖武天皇の発願で天平17年(745年)に制作が開始され、天平勝宝4年(752年)に開眼供養会(かいげんくようえ、魂入れの儀式)が行われた。 その後、中世、近世に焼損したため大部分が補作されており、当初に制作された部分で現在まで残るのはごく一部である。 |
||||
  |
||||
| ★三昧堂(四月堂) | ★法華堂(三月堂) | |||
| 法隆寺の玄関にあたる総門。創建時のものは1435年に焼失し、現在の門は1438年に再建された。 | 8世紀に建てられた東大寺最古の建物で、東大寺の前身とされる金鐘寺の遺構。る。毎年3月に法華会が開かれることから三月堂とも呼ばれる。 | |||
 |
 |
|||
 |
 |
|||
| 若草山 | 公園内の茶店 | |||
| ■春日大社【世界遺産】 |